ページ番号:39032
更新日:2025年3月21日
ここから本文です。
鎌倉市の産業
鎌倉時代~江戸時代頃の産業

治承4年(西暦1180年)に源頼朝が鎌倉入りして、このあと鎌倉幕府を開いて、都市として発展していきました。
鎌倉時代に、船による品物の運搬がさかんになると、和賀江島港を中心にして鎌倉の南東部が商業地域として発展しました。江戸時代には、鎌倉でとれる鰹がもっとも良いものと言われるほどでした。
また、鎌倉時代に漆をなんどもぬり重ねて彫刻する技術が中国からつたわりました。これが鎌倉彫の起源といわれ、茶道の普及とともに「鎌倉物」として有名になりました。
鎌倉市の農業
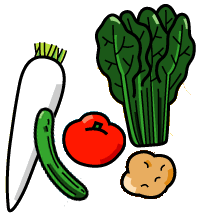
昔は柏尾川や散在ヶ池などから水を引いて水田をつくっていましたが、今では、ほとんどが住宅や工業用地にとってかわりました。
畑も減ってはきましたが、鎌倉は大きい都市の近くであることから、トマト、きゅうり、だいこん、ほうれん草など、新鮮な野菜の出荷が農業の主なものになっています。
鎌倉市の水産業
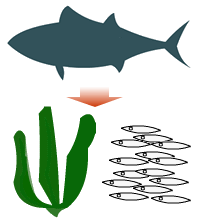
昔は鎌倉は、鰹の生産地として知られ、
"目に青葉、山ホトトギス、初鰹"
という山口素堂という人が江戸時代に作った句が有名になるほどです。
現在の漁業は昔ほどさかんには行われなくなりましたが、いわし、しらす、わかめなどがよくとれて、海産物の店でよく見かけます。
腰越など海岸では、釜揚げしらすやたたみいわしを売って、鎌倉の海をにぎわしています。
鎌倉市の工業
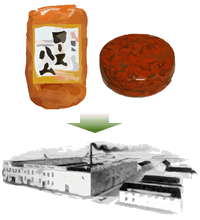
昭和の初めまで工業といえば、古くからの伝統である鎌倉彫・正宗工芸や鎌倉ハム工場などしか目立つものがありませんでした。
しかし、昭和11年(西暦1936年)に松竹撮影所が大船に移ってきてからだんだんと活気がでてきました。
東海道線を利用して大都市へ物が運びやすいことから、大船地区・深沢地区に工場が増えていきました。
電気・機械や化学が主な業種です。
鎌倉市の商業

山と海に囲まれた歴史の町である鎌倉は、海水浴や別荘・文化人居住地で注目され、明治23年(西暦1889年)横須賀線の開通とともに観光客でにぎわうようになりました。
鎌倉駅のまわりは、小売店や飲食店がおおくの観光客でにぎわい、大船駅のまわりは、食料品や生活用品をあつかう小売店やデパート、スーパーマーケットが買物客でにぎわっています。