ホーム > 防災・防犯 > 防災 > 災害に備えて > 災害に関する基礎知識 > 日頃からの地震への備え
ページ番号:1280
更新日:2022年4月6日
ここから本文です。
日頃からの地震への備え
これだけは覚えておきたい10のポイント
1
自分の身の安全を確保する。
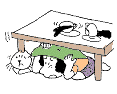
ケガをすると火の始末や、その後の避難行動に支障が生じます。
日頃から家具類などの転倒や移動の防止対策をしておくことが肝心です。
2
すばやく火の始末をする。
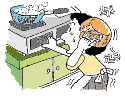
普段から地震の時の火の始末を習慣にしておくことが大切です。
また、火元付近に燃えやすいものを置かないなどの配慮をしましょう。
3
出口を確保する。
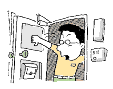
特にマンションなどの中高層住宅では、出口の確保が重要です。逃げ口を失うと、避難することができなくなります。
4
出火した場合はすぐ消火する。
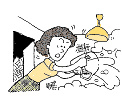
火災が発生した場合でも、天井に燃え移る前ならば、あわてず消火活動を。普段から消火用具の用意を忘れずにしておきましょう。
5
あわてて外に飛び出さない。
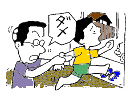
屋外の方が危険な場合も多いので、身の安全と火の始末を図ったうえで、しばらく様子をみるようにしましょう。
6
狭い路地やブロック塀から離れる。

落下物やブロック塀の倒壊などの危険があるので、屋外で地震にあった場合は、ビルや公園などに避難し、危険区域には近寄らないようにしましょう。
7
山崩れ、崖崩れ、津波に注意する。

地震によって山崩れ、崖崩れ、津波が起こり大災害を招くことがあります。居住地の自然環境をよく把握しておくことが二次災害の防止のためにも大切です。
8
避難は徒歩で行う。
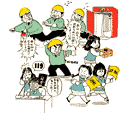
車での移動は渋滞を引き起こし、緊急車両の通行のさまたげになります。また、避難先までは複数の経路が必要です。むやみに避難せず、自主防災組織などの指示に従い、集団で行動しましょう。
9
協力して応急救護を行う。
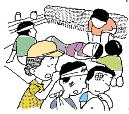
多数の負傷者が出た場合、病院などでの手当にも限界があります。地域ぐるみでの応急救護の体制づくりが大切です。
10
正確な情報を聞く
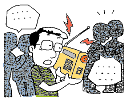
ラジオや市町村、自主防災組織などからの正しい情報を聞き、的確な行動をしましょう。
地震の対処法
屋外
住宅街
- ブロック塀、石塀の倒壊に巻き込まれないように、できるだけ塀から離れる。
- 窓ガラスの破片、屋根瓦などが落ちてくる危険があるので、建物の周りから離れ、広場のようなところへ避難する。
商店街・ビル街
- 頭を鞄などで保護し、最寄りの建物や空き地などへ避難する。ガラスの破片、看板、タイルなどの危険物の落下から身を守る。
- 逃げる場所の判断を的確に行う。間口の広い木造の建物や自動販売機、ブロック塀の側、ビルの壁際などには落下物以外の危険がある。
海岸・がけ付近
すみやかにその場を離れ、安全な場所に避難する。
- 海岸の場合:高台やビルの3階以上に避難する。津波情報をよく聞き、解除されるまで絶対に海岸などの低地には近づかない。
- 崖を背にした家屋:なるべく崖から離れた部屋を生活の中心にしておく。
屋内
家の中
- テーブルなどの下に隠れ、身を守る。余裕のない場合は、手近の座布団や枕などで頭を保護する。
- 外へ逃げ出さない。一瞬にして建物が倒壊することはあまりない。また、屋外は瓦などの落下があるので危険。
- ドアを開けるなどして避難口を確保する。歪みで戸があかなくなることがあるので、団地やマンションなどの中高層住宅では特に、逃げ道を失うことになり危険。
- 2階にいる場合は階下へ降りない。1階より2階の方が安全性が高い。
- 裸足で歩き回らない。ガラスの破片などが散乱している場合があるので、必ずスリッパなどの履物を着用してケガのないようにする。
- すみやかに火の始末をする。この時コンセントを抜くことやガスの元栓の処置も忘れずに行う。
- 乳幼児やお年寄りの安全を確保する。
ビルの中
- 座布団などで頭を保護し、急いで机の下などに身を隠す。
- 本棚などの移動・転倒に注意する。備品のない廊下の方が安全。
- 外は落下物の危険があるので、慌てて外に逃げず、中にいて様子を見る。
スーパー・デパート
- バッグなどで頭を保護し、倒れやすいショーケースなどから離れる。
- 最寄りの丈夫な机などの下にもぐるか、柱や壁際に身を寄せる。
- 係員の指示に従い、階段から避難する。慌てて出口に殺到したりしない。
- エレベーターが止まった場合、中にある連絡電話を使い、救出を待つ。
地下街
- 耐震構造になっており、出口は60メートル間隔。すべての出口がふさがれることはまずないので、壁面や太い柱に身を寄せ、係員の指示に従う。
- 停電になった場合も、非常照明灯がすぐ着くので慌てない。
- 火災が発生した場合は、ハンカチやタオルで鼻と口を覆い、体をかがめ、這うようにして壁づたいに、煙の流れる方向へ逃げる。
劇場・ホール
- 椅子の間にしゃがみこみ、バッグなどで頭を保護する
- 係員の指示に従って外にでる。慌てて出口に殺到したりしない。
乗り物
車の運転中
- 地震を感じたら、徐々に減速し、道路の左側に車を寄せてエンジンを停止させる。
- 揺れが収まるまで車外に出ず、カーラジオで地震情報を聞く。
- 車を離れる時は必ずキーをつけたままにし、ドアロックもしないでおく。
電車・地下鉄の車内
- 急停車にそなえ、吊革や手すりにしっかりとつかまる。
- 途中で停車した場合にも、勝手に非常コックを開けて車外に出たり、窓から飛び出さない。
- 乗務員のアナウンスに従って、落ち着いた行動をとる。
地震に備え、日頃からやっておきたいこと
落下・転倒防止対策
- テレビは低いところに置く
- タンスや棚の上に重いものを置かない
- 本棚やロッカーでは、重いものは下に、軽いものは上に収納する。
- 固定できる家具は固定しておく。
家具の転倒防止
直接柱に固定または間柱、胴縁に固定。家具との間に遊びが出来ないように注意。 (木ねじ、ヒートン、L字金具などを使用)
本棚の本の固定
本棚自身を固定し、さらに各棚ごとにひもで本を固定し、本が飛び出さないようにする。
火災防止対策
- 暖房器具の耐震自動消火装置を定期点検し作動を確認する。
- カーテンはできるだけ防炎加工のものを選ぶ。
- ガスレンジなど火元まわりは不燃化し、整理整頓を心がける。
- 消火器は一定のところに置き、いつでもすぐに使えるようにしておく。
- ガス台の上には棚などをつくらない。
身の安全対策
- 室内にガラスが飛散した場合に備え、スリッパを用意しておく。
- 高さのある家具は、幼児やお年寄りの部屋、寝室にはできるだけ置かない。
- 階段に滑り止めや手すりをつける。
家の外の対策
- プロパンガスのボンベは鎖でしっかりと固定する。
- ブロック塀や石垣の崩れは修繕し補強する。
- 不安定な屋根瓦や、屋根の上のアンテナは補強する。
- ベランダの植木鉢は落下などしないように整理整頓する。
非常持ち出しの備え
災害時に備えて、日頃から持ち出し品の準備をしておきましょう。
家庭での備え
災害が発生してから救援体制が整うまで、約3日間かかると言われています。その間を自分たちの力で乗り切るために、次のような防災資機材などを準備しておきましょう。
非常食(家族3日分の量を準備)
- 飲料水(水筒・ビン入りなど)
- カンパン
- 缶づめ類と缶切り
- ビスケット
- インスタントラーメン
救急セット
- 消毒薬
- 傷薬
- 脱脂綿
- 包帯
- 三角巾
- 副子
- ガーゼ
- 絆創膏
- はさみ
- 家庭常備薬
衣類
- セーター
- ジャンパー
- 下着1~2枚
- 靴下
- タオル・石けん
- 軍手・厚手のゴム手袋
- 毛布または寝ぶくろ
- シーツ
- 風呂敷
- 厚底の靴
- ヘルメット
- 防塵メガネ
- 防塵マスク
消防用具他
- 家庭用消火器
- 三角消火バケツ
- 水バケツ
- 投てき水パック
- ペンチ
- ハンマー
- バール
- 鋸(片刃式)
- スコップ
その他
- 警笛
- 現金
- 預金通帳
- 印鑑
- 証書類
- 懐中電灯
- ローソク
- マッチ・ライター
- トランジスタラジオ
- サラシ1反
- 防水ビニールシート
- 組ひも
- ナイフ
- 自転車
赤ちゃんがいる場合
- 粉ミルク
- ほ乳びん
- 紙おむつ
お年寄りがいる場合
- タンカ
- 看護常備薬
- おむつ
組織での備え
組織で準備するものには、倒壊した建物をとり除くための大バールや大ハンマー、負傷者の搬送するための担架など比較的大きな防災資機材が必要です。
- 街頭設置消火器
- 町内備蓄消火器
- 街頭設置防火用水
- 大バール
- 大ハンマー
- たがね
- 掛矢
- 鉄パイプ
- 斧
- 鉄線鋏
- 丸てこ棒
- チェーンソー
- 可搬ウィンチ
- 鉄筋カッター
- 角材
- はしご
- ロープ
- 自動車用ジャッキ
- ツルハシ
- モッコ
- 可搬式発電機
- 投光機
- コードリール
- 救急セット
- リヤカー
- 折り畳み式担架
- 車いす
- 旗(堤灯)
- 任務別腕章
- 携帯拡声器
- 回覧板
- 掲示板(安全確認・伝言)
- 炊飯設備
- 浄水機
- 簡易トイレ
お問い合わせ
所属課室:市民防災部総合防災課防災担当
鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階
電話番号:0467-23-3000