ページ番号:3416
更新日:2021年4月5日
ここから本文です。
鎌倉駅周辺地区交通計画懇談会
はじめに
|
今小路通りは、鎌倉駅の西側を若宮大路と並行して南北に伸びており、その道路幅員は約7m程度と、歩道を設置することが難しい交互通行の狭隘な生活道路です。しかし、土曜日や休日ともなると、若宮大路の渋滞を避けて都心方面への帰路につこうとする観光交通が入りこみ、平日とは一転して大変な交通混雑が発生します。その一方で、この道路は、鎌倉駅西側に点在する観光資源へのアクセス道路でもあり、観光を目的とした多くの歩行者が通行します。このため、自動車と歩行者が輻輳し、交通安全上望ましいものとはいえません。このような状況は、沿道に住まう市民の生活にも大きな支障を来しており、何らかの対策を求める非常に多くの声が市にも寄せられていました。 |
|
今小路通り周辺案内図
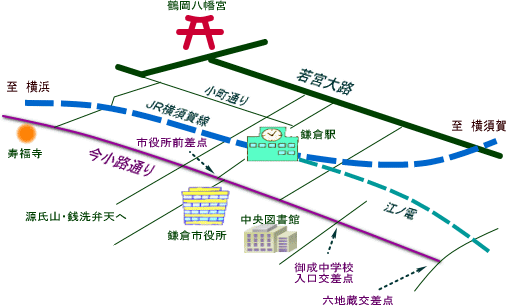
今小路通り歩行者尊重道路の検討
1:鎌倉駅周辺地区交通計画懇談会
多くの住民からの要望が出された今小路通りの交通環境改善策については、「鎌倉地域交通計画研究会(以下、「研究会」という。)」が平成8年5月に出した「鎌倉地域の地区交通計画に関する提言(以下、「提言」という。)」において、歩行者尊重道路として位置付けられました。これは、従来の歩車共存道路よりも「歩行者や自転車を優先させた道路」という考え方です。
今小路通り歩行者尊重道路の実現に向けては、当初、提案者である研究会が計画の具体化を進めていくことも考えられましたが、特にこの施策については、沿道住民に大きな影響を与える可能性があると判断され、鎌倉地域全体の交通環境改善を目的とする研究会が検討するよりも、施策の影響を直接受けると思われる沿道住民が詳細な施策内容を検討するほうが望ましいと考えられました。
そこで市は、今小路通り周辺の13自治町内会、9商店会から代表者を募り、研究会とは別に「鎌倉駅周辺地区交通計画懇談会(以下、「懇談会」という。)」を設置し、平成11年3月から、今小路通りにおける歩行者尊重道路のあり方について検討を始めました。
なお、この懇談会では、個々の委員が各々の考え方を自由に発言でき、かつ活発な議論の展開を図るため、3つのグループに分かれてワークショップ形式による検討を行うこととしました。
(ワークショップとは、同じ目的を持って何かを作り上げるために人々が集まり、異なる感性や異なる経験に基づく考え方を出し合って、少しずつ自分たちの考え方をまとめあげていく手法です。)
懇談会と研究会の関係
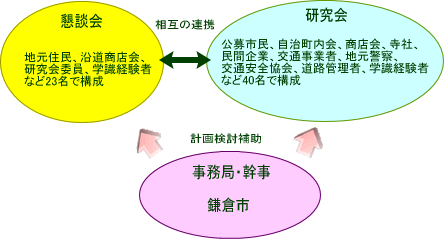
2:将来計画素案の作成
(1)道づくりの考え方
提言では、通過交通が流入しやすい生活道路において、自動車の走行に抵抗を与えることによって歩行者尊重道路を整備することとしています。懇談会では、この考え方を踏襲することとしました。また、今小路通り歩行者尊重道路という施策を実施することによって、近接する周辺の幹線道路への影響も考えられますが、これについては、20の施策を複合的にすることで、その影響を低減させるものと考え、懇談会における検討内容とは切り離すものとしました。
また、今小路通りにおける適切な交通量を考えた場合、「細街路の住環境に関する調査(D.アップルヤード、M.リンテル)によると、交通量と居住環境とは密接な関係を持っていると示されており、今回の計画では、居住者や観光客が安心して歩ける道路とするために、軽街路(ピーク時交通量=約200台)を目標として計画の策定に取り組むこととしました。
(2)懇談会で合意された5つの基本事項
先に示した目標を達成するに当たり、懇談会では次に示す5つの事項を検討の基盤に置くこととしました。
●休日における今小路通りの道づくりのあり方を考える。
●歩道と車道を一体と考えて、交通弱者の通行に配慮した人にやさしい歩きやすい道とする。
●自動車の交通量は、できる限り抑制する。 通過交通をなくして流れをスムーズにするため、地域住民も多少の不便は共有することも必要である。
●自動車の速度は、できる限り抑制する。
●通過交通をなくすだけでなく、地域住民も自動車利用を抑制すべきである。
|
|
|
|
各グループごとに自由な議論を行う |
模型などを用いて様々な角度から検討 |
(3)将来計画(素案)
これまでにイメージされた今小路通り歩行者尊重道路を実現するために、懇談会では5つの基本事項に従って、現在の交通規制の見直しや道路幅員の有効な利用方法をより具体的に検討し、いくつかの将来計画(素案)を作成しました。
今小路通り歩行者尊重道路将来計画(素案)の一例
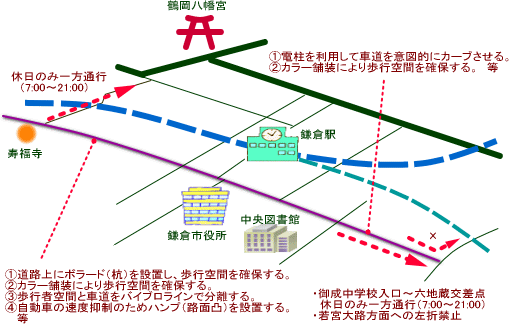
注:この将来計画(素案)は、検討途中に提案されたものであり、将来計画として決定したものではありません。
社会実験の実施
懇談会では、3つのグループから出された複数の将来計画(素案)をもとに、より効果的かつ実現可能な将来計画(案)を作成するため、「今小路通り歩行者尊重道路社会実験」を実施することとしました。
この社会実験では、素案の効果や課題を見極めるために、それぞれの素案から重要となる仕掛けを選択し、今現在社会実験として実施可能と思われるもの(期間を限定した一方通行化や仮設のハンプ)を組み合わせ、社会実験計画(案)を策定しました。
また、社会実験計画(案)を策定した後、地元市民の意見も実験計画に反映させる必要があると考え、「今小路通りを考える会」を開催し、社会実験計画を確定しました。
社会実験の概要
実施日等…平成11年11月13日(土曜日)・14(日曜日)・20日(土曜日)・21(日曜日)の10時~16時
今小路通り歩行者尊重道路社会実験の様子
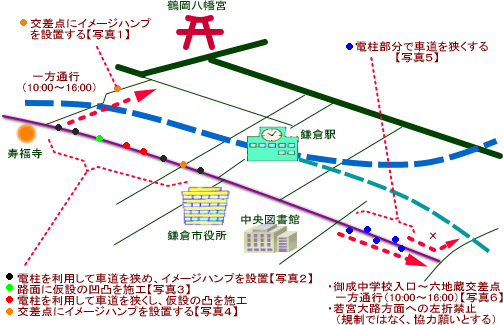
|
(JPG:75KB) |
(JPG:61KB) |
(JPG:54KB) |
|
写真1 |
写真2 |
写真3 |
|
(JPG:67KB) |
(JPG:63KB) |
(JPG:59KB) |
|
写真4 |
写真5 |
写真6 |
|
→それぞれの画像をクリックすると拡大表示されます |
実験の結果
4日間の社会実験と合わせて様々な調査を実施した結果、次のことが確認されました。
1:交通量調査の結果
先にも説明したとおり、今小路通りにおける適正な交通量の目標は、ピーク時(1時間当たり)交通量を200台程度に減少させることでした。
今回の社会実験時の交通量を4つの地点で計測し、平成8年11月3日の交通量と比較した場合、若干減少はしたものの、300台~700台となっており目標とするピーク時交通量には至りませんでした。
これは、施策が周知される前に、4日間という短い実験期間が終了してしまったこと、提言にある20の施策全てが実施されていなかったため、鎌倉地域全体の自動車交通量が充分に抑制されなかったことなどが考えられます。
2:歩行者交通量
歩行者交通量のピーク時間は14時~15時となっており、その時の歩行者交通量は、市役所前交差点~寿福寺付近で800人~900人でした。このうち約3割程度が、車道部分を歩行しており、道路構造令における歩道設置の判断基準「概ね一日の歩行者が100人以上、自動車が500台以上の道路」にも該当することから、歩車を分離する対応策が必要であると考えられます。
3:アンケート調査、ヒアリング調査の結果
全体的な傾向として、来訪者は社会実験の試みに対する評価が高く、今小路通り沿道の駐車場利用者も、それほど不便さを感じてはいませんでしたが、自動車を利用する市民、商業者、交通事業者(タクシー会社、宅配会社)は、日常生活や営業に対する影響があると感じているようでした。
このことから、今後は、施策の考え方に対する理解を深めるとともに、影響を最小限に押さえるための方策を検討していく必要があります。
将来計画(案)
社会実験を経て、様々な効果や課題を確認した結果、「1交通規制の考え方」と「2歩行者・自動車の分離及び速度抑制」という2つの観点に分け、それぞれを自由に組み合わせることのできる「今小路通り歩行者尊重道路将来計画(案)」を作成しました。
将来計画(案)~交通規制の考え方~
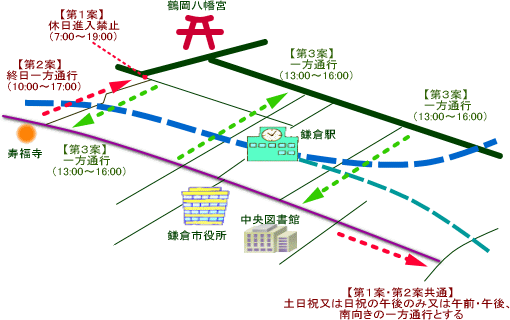
|
施策の主なメリット |
施策の主なデメリット |
|
|
第1案 |
・旧川喜多邸前区間を進入禁止にすることで、車の擦れ違いに伴う交通渋滞の解消、歩行空間の確保等が期待される。 ・御成中学校入口から六地蔵交差点を一方通行にすることで、八幡宮方面への抜け道とはならなくなり通過交通の抑制が期待される。 |
・この区間の住民が市役所方面へ移動するのに不便を強いられる。 ・商用車への大きな影響が考えられる。 |
|
第2案 |
・旧川喜多邸前区間を一方通行とすることで、車の擦れ違いに伴う交通渋滞の解消、歩行空間の確保等が期待される。 ・御成中学校入口から六地蔵交差点を一方通行にすることで、八幡宮方面への抜け道とはならなくなり通過交通の抑制が期待される。 |
・この区間の住民が市役所方面へ移動するのに不便を強いられる。 ・旧川喜多邸周辺住民が線路西側へ移動する場合、不便を強いられる。 ・商用車への大きな影響が考えられる。 |
|
第3案 |
・通過交通を抑制するためには、最も効果的な交通規制である。 | ・小町踏切の道路へ自動車が集中し、小町通を横断する車が増えるため、渋滞を招くことも考えられる。 |
将来計画(案)~歩行者・自動車の分離及び速度抑制~
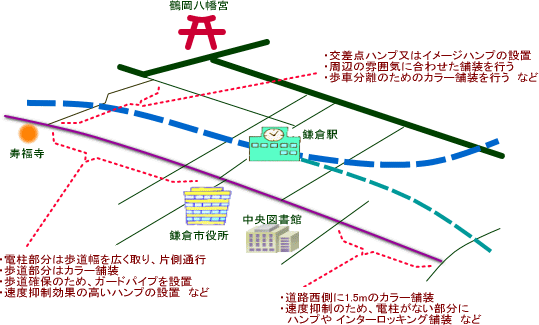
今後の取り組み方針
1:施策の主旨や目的を地域住民に説明し、理解を得ながら進めていく。
今後は、懇談会委員意外の市民一般に提案の内容を広く周知し、この施策について議論を広める必要がある。 そのためには、この提案を報告する機会を数多く設けるとともに「継続的な議論の場の提供」を行なうようにする。
2:多面的な広報PR活動を行い、施策緒周知徹底を図る。
この提案は、交通規制の変更等を含めて広域的な影響を考慮すべき内容を含んでいる。従って、広範囲を対象とする多面的な広報PR活動を積極的に実施する。
(1)各種広報誌の活用
(2)市民等への説明か、市民等との意見交換会、公開討論会、イベントの実施
(3)インターネットを活用した情報提供
(4)アンケート調査の実施(周知活動)
(5)社会実験の実施(周知活動)
3:施策の推進に当たっては、引き続き行政と市民が協働して取り組みを進めて行く。
1、2を推進し、この施策を実現するための具体的な手法として、行政と市民が協働して取り組むための新組織(協議会等)を設立するとともに、常に市民等との意見交換を行なえる仕組みを工夫する。
また、施策を効果的に実施するため、次のような制度の活用に向けた検討を行う。
(1).特定交通安全施設等整備事業(コミュニティ・ゾーン形成事業)
(2).社会実験への支援制度
懇談会に関する資料








