ページ番号:3430
更新日:2021年10月15日
ここから本文です。
鎌倉市オムニバスタウン計画
はじめに
鎌倉市における交通政策は、平成8年度に策定した「第3次鎌倉市総合計画」において、「交通需要管理計画の検討」と「公共交通機関の輸送力向上」の2つを柱としています。このうち交通需要管理計画の検討については、交通混雑の最も激しく、かつ新たな道路を整備することが難しいが鎌倉地域において様々な取り組みが行われているところですが、「公共交通機関の輸送力向上」については、市域全体の問題であると捉え、全市的な視点に立って検討を進めているところです。
こうした中、鉄軌道系の公共交通を新たに整備することは、莫大な費用と時間を費やさなければならず、極めて困難であることは周知のとおりです。
そこで市は、「公共交通機関の輸送力向上=バス交通の充実」という考え方を基本に、バス交通に関連する施策を重点的に推進することとしました。
オムニバスタウン計画とは
オムニバスタウン計画とは、警察庁、運輸省、建設省(共に、現国土交通省)、が推奨する「オムニバスタウン構想」に基づくものであり、マイカーに比べて、人、まち、環境にやさしいバス交通を充実させることにより、自動車事故、渋滞等まちが抱える交通問題の解決を図ろうとする計画をいいます。
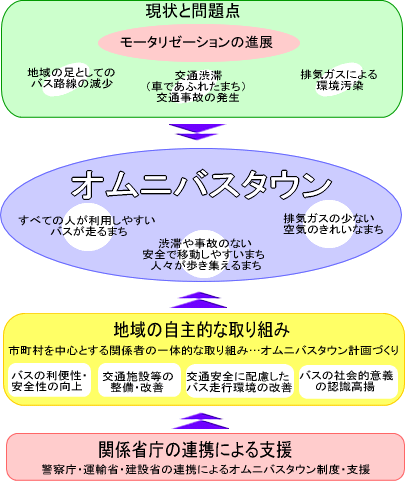
鎌倉市では、平成9年度に「鎌倉市バス交通体系整備調査」を実施した後、平成10年4月に公募市民、バス事業者、関係行政機関、学識経験者等で構成する「鎌倉市オムニバスタウン計画策定協議会」を立ち上げ、1年間の議論を経て「鎌倉市オムニバスタウン計画(案)」を作成、翌平成11年度に、この(案)を行政計画として位置付け、同年度に国内では5番目の「オムニバスタウン」として、国の指定を受けました。
この結果、バス事業者、市、国が協調して「バスの有する多用な社会的意義を最大限に発揮するまちづくり」を推進するため、「鎌倉市オムニバスタウン計画」にある事業を実施していくこととなりました。
『オムニバス=Omnibus』とは 乗合バスの語源で、もともとは「何の御用にでも役立つ」という意味。乗合バスの発祥期に、フランスの乗合馬車発着所になっていた雑貨屋の看板に、こう書かれていたことにちなみます。現代においては、地域の足・まちづくり・環境問題等の“多様な社会的課題の解決の御用に役立つ”という意味が込められています。
鎌倉市オムニバスタウン計画
1:基本理念
鎌倉市におけるバス交通は、「安全性」、「正確性」、「快適性」を備え、かつ低廉な料金で快適に移動することが可能な「市民の足」として役割を担ってきました。
しかし、近年の交通渋滞などによる交通環境の悪化は、バス交通の定時性、信頼性、円滑性を低下させ、身近な移動手段としての機能を充分に発揮できていません。
鎌倉市におけるオムニバスタウン計画では、
(1)バス運行ルーとの充実
(2)公共交通機関相互の連携強化
(3)バスの走行環境の総合的向上
(4)バス交通における移動制約者への配慮
(5)バス交通における環境への配慮
(6)バス交通のまちづくりへの活用
という課題解決を目指します。
また、古都鎌倉の歴史的資源、自然環境を生かしつつ、バス交通の役割が最大限に発揮されるまちづくりを推進するため、バス交通の信頼性を回復し、市民生活に根ざしたバス交通体系の実現を図るものとして、次の基本理念のもとに計画の展開を図ります。
鎌倉市オムニバスタウン計画の基本理念
「鎌倉の環境と市民生活とが調和したバス交通の創造 」
2:基本方針
前述した6つの課題を解決し、基本理念を実現するため、次のとおり基本方針を定めます。
(1)利用者の立場に立ったバスサービスの充実
(2)公共交通機関相互の連携が図られたバス交通体系の実現
(3)バス走行環境の総合的向上
(4)移動制約者が利用しやすいバス交通の実現
(5)環境負荷の小さなバス交通の実現
(6)バスの利用促進に向けた意識の高揚
3:取り組み方針
鎌倉市オムニバスタウン計画では、課題の優先度や施策実施に要する期間などを考え合わせ、段階的に取り組みを進めていくととします。
段階的にとは、整備期間を短期(平成11年度~15年度)、中期(平成16年度~20年度)、長期(平成21年度以降)に区分し、施策の実現に取り組むものです。
また、それぞれの期間における目標を次のように定めます。
(1)短期計画における目標:バスを利用しやすい環境の創造
バス利用の可能な地域の拡大を図り、バス交通の基本的な役割である「市民の足」の確保を目指すとともに、鉄軌道が比較的充実している鎌倉市の特性を生かした乗り継ぎのしやすさの向上、短期間に整備の可能な走行環境の改善による定時性の向上を図る等、バスを利用しやすい環境の創造に努めます。
これにより、バス利用の促進やバスのイメージアップを図ります。
(2)中期計画における目標:バス運行ルーとの充実と公共交通相互の連携強化
多様化する市民ニーズに対応して利便性の高いバス運行ルートの充実を図ることにより、使用しやすいバス路線の形成を目指します。また、公共交通相互の連携強化や道路の有効活用と整備を図ることにより、総合的な走行環境の改善を目指します。
このため、短期に実施したバス交通整備方策の更なる充実を図るとともに、事業実施に期間を要する方策の実現を推進します。
(3)長期計画における目標:市民生活に根づいた公共交通の実現
鎌倉市オムニバスタウン計画の基本理念である「鎌倉の環境と市民生活とが調和したバス交通の創造」を総合的に実現することを目指します。
このため、これまでに実施されている方策の充実を図り、バス交通の役割が最大限に発揮され、那須を生かした鎌倉らしいまちづくりを推進します。
4:段階計画と整備施策
短期、中期、長期計画と整備施策を次表のように定めます。
|
整備施策 |
短期 |
中期 |
長期 |
||
|
バスを利用しやすい環境の創造 |
しやすい環境の創造 バス運行ルーとの充実と公共交通相互の連携強化 |
市民生活に根づいた公共交通の実現 |
|||
|
利用者の立場に立ったバスサービスの充実 |
主要施策 |
鎌倉型バスシステムの創造 |
〇 |
〇 |
|
|
公共施設へのアクセスバス路線の整備 |
|
〇 |
|
||
|
観光施設循環バス路線の整備 |
|
〇 |
|
||
|
時間帯別運行ルーとの導入 |
|
〇 |
|
||
|
補完施策 |
フリー乗降システムの導入 |
〇 |
|
|
|
|
機能的なバス停留所の整備 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
|
鎌倉フリー環境手形の導入 |
〇 |
〇 |
|
||
|
環境定期券の導入 |
〇 |
〇 |
|
||
|
幹線・支線バス路線の整備 |
〇 |
〇 |
|
||
|
バス運行状況案内システムの導入 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
|
公共交通機関相互の連携が図られたバス交通体系の実現 |
主要施策 |
鎌倉駅、大船駅でのターミナル機能の強化 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
乗り継ぎ運賃制度の導入 |
〇 |
〇 |
|
||
|
補完施策 |
ターミナル駅へのマイカー乗り入れ規制 |
〇 |
〇 |
|
|
|
バス走行環境の総合的向上 |
主要施策 |
バス専用、優先レーンの設置 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
道路改良等の整備 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
|
パーク&バスライドの導入 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
|
補完施策 |
バスベイの整備 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
公共交通優先システム(PTPS)の導入 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
|
違法駐車対策 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
|
荷捌き対策 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
|
移動制約者が利用しやすいバス交通の実現 |
主要施策 |
ノンステップバス等の導入 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
環境負荷の小さなバス交通の実現 |
主要施策 |
低公害バスの導入 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
地域に応じたバス車両の導入 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
|
バスの利用促進に向けた意識の高揚 |
バス利用促進のためのイベント等の開催 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
鎌倉市オムニバスタウン計画として推進すべき整備施策は、基本方針の実現に直接的な効果が期待される施策を優先して取り組む必要があります。このため、これら基本方針を実現するために直接関連のある整備施策を「主要施策」としました。
さらに、基本方針を実現する上で、単独で実施するだけでは効果が低いものの、主要施策と一体的に実施することで、より高い効果を発揮する整備施策を「補完施策」としました。
5:鎌倉市オムニバスタウン計画の概要
鎌倉市オムニバスタウン計画をまとめると、次のとおりとなります。
→鎌倉市オムニバスタウン計画概要図はこちら(PDF:200KB)
施策の推進体制
1:協議会の設立
鎌倉市オムニバスタウン計画の推進に当たっては、市民、事業者の意向や要望を充分に把握した上で、関係機関の間で調整を図りながらしさくを実施する必要があります。このため、市民、バス事業者、行政を中心とした計画の推進組織を設置し、様々な意見を反映しながら計画を推進する体制を確立します。
2:適正な役割分担による施策の実施
鎌倉市オムニバスタウン計画における整備施策の実施は、鎌倉市をはじめとする行政機関、バス事業者、その他の機関が主体となって実施することとなります。整備施策は、それぞれの実施主体の権限の範囲において、適正な役割分担のもとに実施するとともに、関係機関等と充分な調整を行い、関係機関が密接な連携を図って進める必要があります。
最優先課題への取り組み
鎌倉市オムニバスタウン計画では、整備期間を短期(平成11年度~平成15年度)、中期(平成16年度~平成20年度)、長期(平成21年度以降)に分けて、段階的に取り組みを進めていくこととしましたが、最優先課題として掲げられているのが「鎌倉型バスシステムの創造」です。
これは、鎌倉の特徴ともいえる多くの狭隘道路において、人と環境にやさしい「小型・低床・低公害」の車両を使ったコミュニティーバスを運行し、「市民の足」となるバス路線を確保することで、市域に存在する「交通不便地域」の解消を図ろうとするものです。
計画開始後の5年間は、これを目標として取り組みを進めていくこととします。